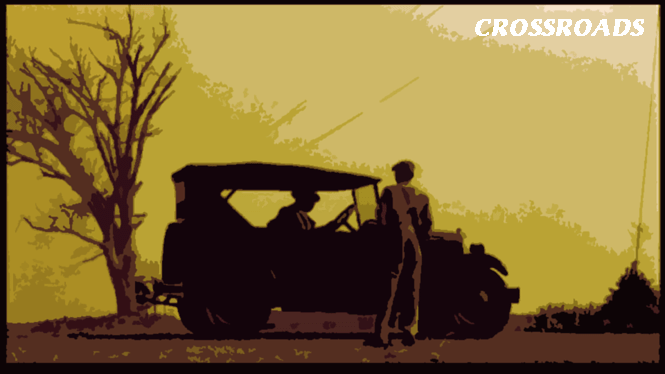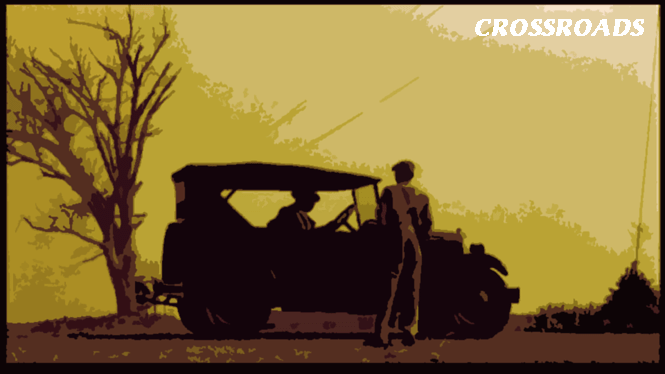|
つまり良くも悪くも極東の平和な島国〜日本で生まれ育ったオレでは、“ブルース”といった“黒人文化”を受け入れ憧れる事は出来ても、「おそらく自分がソコに辿り着くことは、永遠に叶わないだろう」と諦観せざるを得ないワケでさ。
加えてリズム&ブルースの進化した形でもあるロックンロールですら、結局は黒人と白人(というより、米国と英国)の音楽なのだから悲しいもんである。
そりゃ、日本ナイズされたロックは沢山あるし、好きなミュージシャンも大勢いるが、さ。
何か愚痴ばかりになってきたので、ここらで話を元に戻しますかね(笑)
ま、映画ってのは、観る人間に夢を与えてくれるからね。
クロスロードの主人公〜ユージンに自己投影して、伝説のハープ奏者を探し出し、2人だけで路銀も持たずにエレキ片手にアメリカ南部〜ブルースの旅ができるのだ。
ブルース・サウンドにまつわる厳しさや、優しさ、辛さ、楽しさが、かなりリッチな気分で擬似体験できるのだから、こんなに楽しい事はないっス(ついでに、行きずりの女の子とのブルージーなラブロマンスもね)
ウォルター・ヒル自身も「そのつもり」で撮ってるんだろうし……そう考えればこの映画、ひどく私小説的な作品とも言える。
|