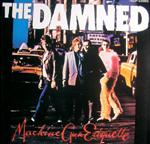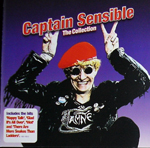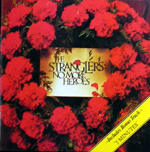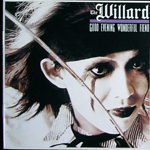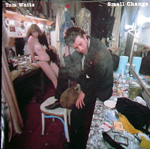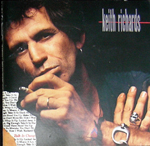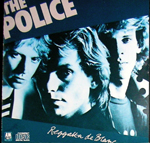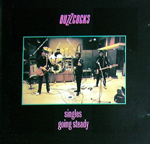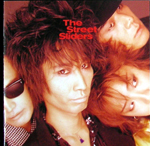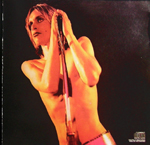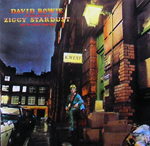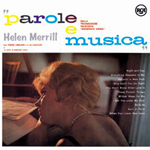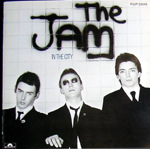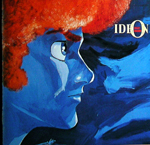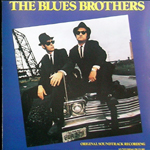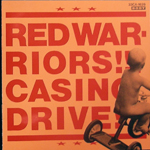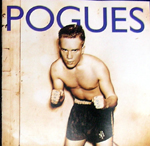Welcome !
PRIVATE CD REVIEW
Page: 1 | 2 | 3 |
|
FAVORITE CD Act.001 THE DAMNED - MachineGun Etiquette
|
|
FAVORITE CD Act.002 CAPTAIN SENSIBLE - The Collection
|
|
FAVORITE CD Act.003 THE STRANGLERS - No More Heroes
|
|
FAVORITE CD Act.004 THE WILLARD - Good Evening Wonderful Fiend
|
|
FAVORITE CD Act.005 TOM WAITS - Small Change
|
|
FAVORITE CD Act.006 KEITH RICHARDS - Talk Is Cheap
|
|
FAVORITE CD Act.007 BURT BACHARACH - Casino Royale
|
|
FAVORITE CD Act.008 THE POLICE - Regatta De Blanc
|
|
FAVORITE CD Act.009 BUZZCOCKS - Going Steady
|
|
FAVORITE CD Act.010 NAZZ - Nazz
|
|
FAVORITE CD Act.011 THE STREET SLIDERS - Angels
|
|
FAVORITE CD Act.012 ENNIO MORRICONE - Le Colonne Sonore Originali Dei Film Di Sergio Leone
|
|
FAVORITE CD Act.013 IGGY & THE STOOGES - Raw Power
|
|
FAVORITE CD Act.014 DAVID BOWIE - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust
|
|
FAVORITE CD Act.015 HELEN MERRILL - Parole E Musica
|
|
FAVORITE CD Act.016 THE JAM - In The City
|
|
FAVORITE CD Act.017 すぎやまこういち - 伝説巨神イデオン
|
|
FAVORITE CD Act.018 THE BLUES BROTHERS - The Blues Brothers Original Soundtrack
|
|
FAVORITE CD Act.019 RED WARRIORS - Casino Drive
|
|
FAVORITE CD Act.020 THE POGUES - Peace And Love
|
Page: 1 | 2 | 3 |
HOME