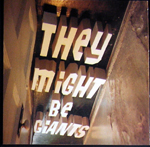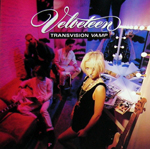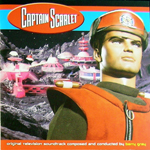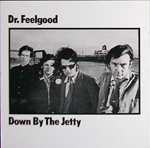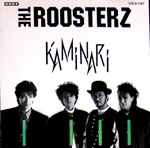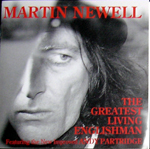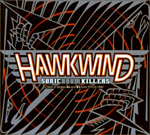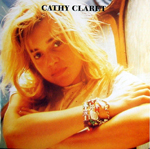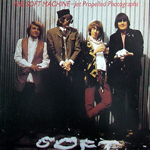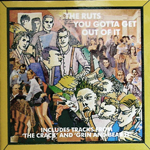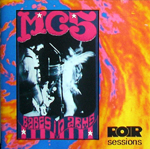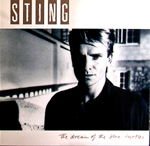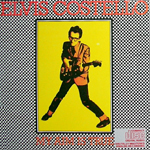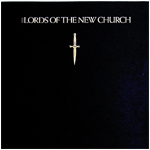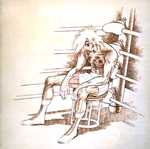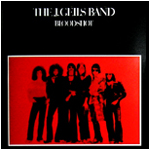「キャプテン・センシブルが好き」とか書いてる時点で、いずれこのコーナーで“They Might Be Giants”(以降TMBG)や“XTC”などを取り上げるであろう事を予測した諸氏も、かなりいたハズ
まぁ、まさにその通りなワケで、返す言葉も無いオレなのだが(苦笑)
で、TMBGサウンドってのを簡単に表現すれば、打ち込み系ブリティッシュ調ポップチューンの王道なんである。
こういった、文字通りに“玩具箱を引っくり返したような”シニカルでワクワクハッピーな音楽性って、個人的に大好きなんだよなぁ。
ただ初めに驚いたのが、このTMBGのメンバー(アコーディオン弾きのジョン・リンネルとギターのジョン・フランズバーグ)が、実は2人とも生粋のニューヨーカーって事である。
何故此れほどまでに洗練された、如何にもな英国風サウンドに仕上がっているんだ?
――という疑問も、バンド名の由来が映画“They Might Be Giants(1971)”からだという事を知って、すんなり納得。
この映画、自分をシャーロック・ホームズだと思い込んだパラノイアが主人公なのだな(笑)
なるほどねぇ……英国風に傾倒するワケは勿論、皮肉が効いた演劇性の根っこの部分すらも良くわかる逸話であります。
で、初期から中期にかけてのアルバムの中で、特に良い意味でラフに弾けたカンジのこのB-sideコレクションを、個人的な彼らのベストに推しまする。
特に“For Science”〜“(She Was A) Hotel Detective”の流れは、最高に格好良いポップロックですな(間に挿まれたミニドラマを省いて聴くのが、ノリとしてなお良し)
今回は選ばなかったが、3rdアルバムの“FLOOD”も負けず劣らず素晴らしいっすよ〜
だが5枚目のアルバム“John Henry”以降、リズムボックスによる打ち込みをやめて所謂バンド編成になってしまい、魅力の大きなウェイトを占めていた“チープさ”が薄れてしまったのは残念至極である。
楽曲自体は悪くないのだがねぇ……普通のバンドになっちまったっていうかさ(生音が悪いってのも、妙な話ではあるが。しかし以降のTMBGに個人的な興味が無くなってしまったのも事実)
最近はディズニーで活動しているらしいが、マジにキッズ向けにしてどうするよ……シャレにならんだろ、一時期のスピルバーグあたりと同じでさ。
|
|